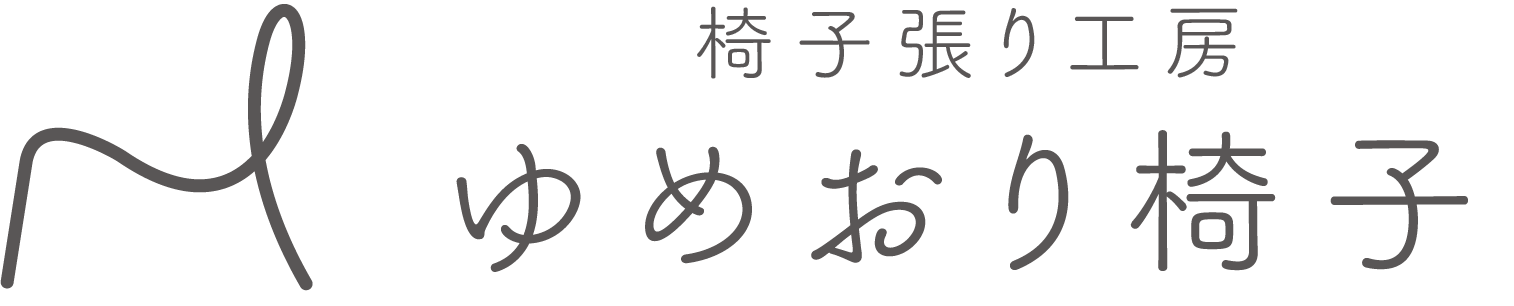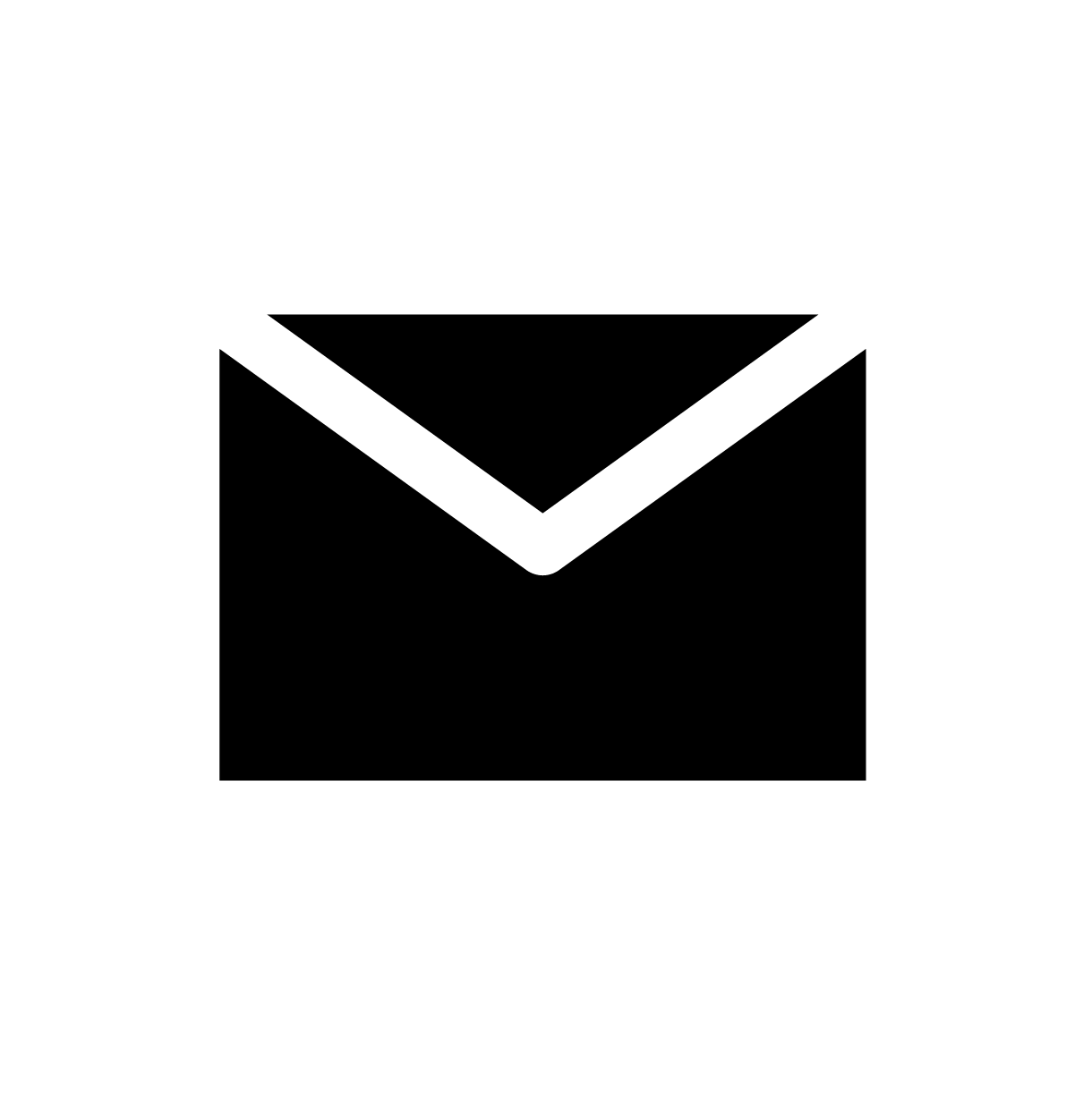秋の新作生地 その2
国内の工場を見学したい申し出は幾つもするのですが、
なかなかこういった単体の工房では難しいこともしばしば。
工場見学に行くときのメインの目的は普段目にすることのない製造現場で
直に聞くことのできる情報や見て感じることのインスピレーションですが、
それ以外にもその土地で育まれている歴史や風土を肌で感じる喜びも大きくあります。
今回のOLTAS(オルタス)の椅子生地の工場見学では、
岐阜県の羽島市に行ってきました。
なぜこの場所にOLTASが在るのか?
そして、そのような場所で商売が成り立つのか?
調べていくと、面白いことがどんどん分かってきました。
この辺りは、「尾州」と呼ばれている地域。
イタリアのビエラ、イギリスのハダースフィールドと並ぶ、毛織物の世界三大産地です。
産地の最大の特徴としては、糸から織物を作るまでの全工程がこの地域でなされ、
分業体制が整っていることです。
尾州産地は、木曽川流域の豊かな自然に恵まれていたため、
昔から織物生産が盛んに行われてきた土地です。
1200年以上前から、麻、絹、綿と時代時代にあわせて生地を生産していきました。

古くは弥生式遺跡から発見された土器の底面につけられていた布の痕跡。
1200~1300年前とされる現存する最古の布片などから麻織物がこの地方で作られていたようです。
また正倉院に現存する尾張国正税帳(天平6年:734年)によれば、
当時すでに綾及び綿などが盛んに織られていたことがわかります。
加えて、江戸・元禄期(1688~1704年)には
「春雨や桑の香に酔う美濃尾張」(其角)という句が詠まれるなど、
美濃・尾張一帯では桑が栽培され、絹織物が盛んであったと知られています。

1540年代になると琉球から薩摩を経て、
内地に綿栽培が伝わり江戸時代に盛んになりました。
戦国時代以来、木綿は実用向きとして絹布を凌ぎその栽培が進み、
江戸・藩政時代の尾張平野は秋祭りの頃になると見渡す限り綿の白で溢れ、
住屋も生綿の山となったそうです。

1842年の尾張国産品のうち織物類に
桟留縞(さんとめじま)、結城縞、繰綿、さなぎ糸、絹、かぴ丹、糸類、羽二重が
挙げられているのをみると、相当生産されていたのが窺えます。