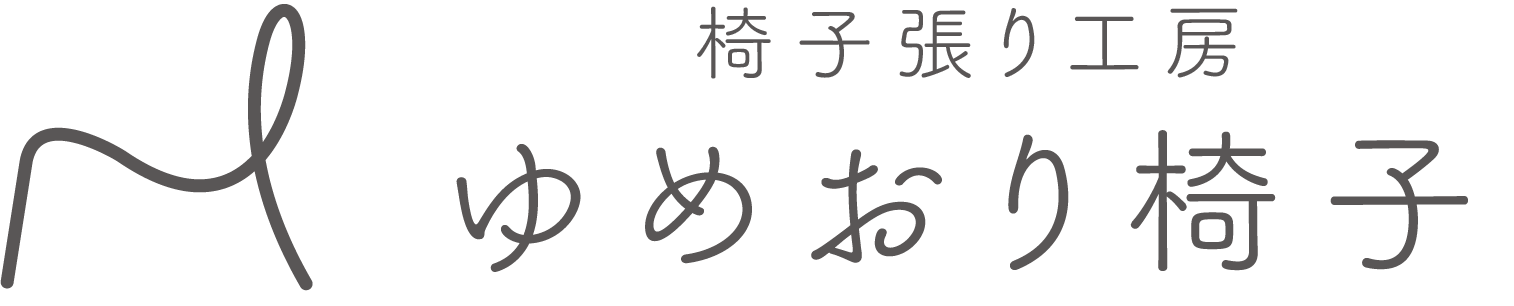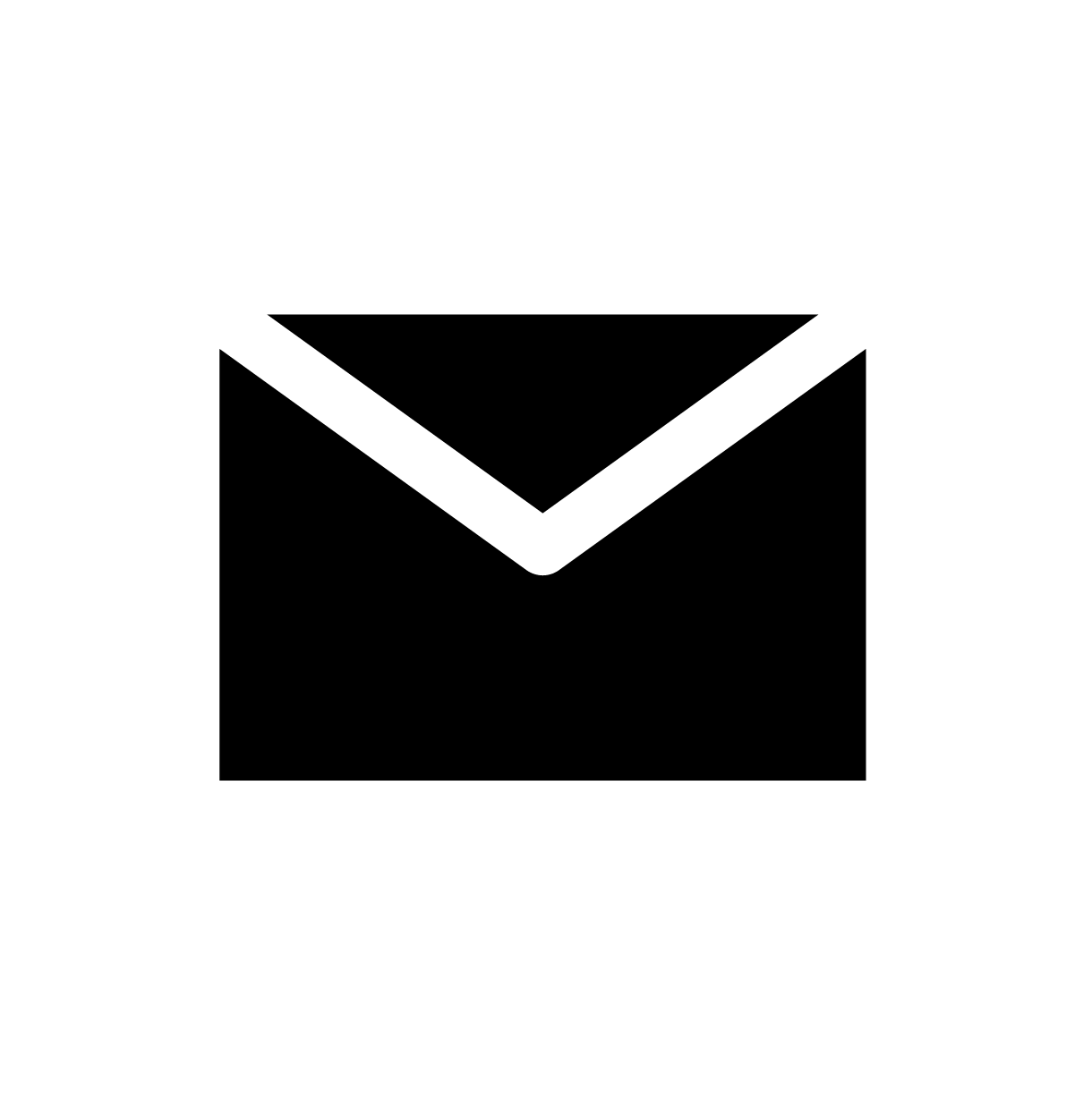秋の新作生地 その3
大正3年(1914年)第一次世界大戦が勃発。
軍服を作るために毛織物の需要が高まり、
輸入が途絶えてしまいます。
日本では和装から洋服化への需要量は激増したにもかかわらず、
その在庫は底をつき服地業者は窮地に立たされました。
その一方で国産品愛用が唱えられるようにもなりました。
これを機に、尾州が毛糸を用いて織った和服用織物が
全国的な特産地として名声を博することとなりました。
こうして、尾州の毛織物の生産量は僅か5年で
20倍に激増、全国生産の約70%を占めるまでに至りました。

大正期以降も、洋服地用の毛織物の研究・生産に取り組み始め、
昭和60年代前半、天然繊維ブームや婦人こども服の普及により、
毛織物の生産量が更に増大しました。
そのような土地へ向かう道中もあれこれと考えを巡らせ楽しかったです。
織物工場へ行った際、まず驚いたのが音!
『がちゃんこ!がっちゃんこ!がっちゃんこ!・・・』と、
機械の心地よいリズム音。
(このあたりの音は、ゆめおり椅子のInstagramに動画がアップされています。)
音を聞きたい方はこちら https://www.instagram.com/yumeori_chair/?next=%2F

工場では、戦後日本のモノ作りを支えてきた生地職人さんが出迎えてくれました。
中に入ると、アンティークな風合いのある大きな織機が動いています。
一定の動きを繰り返し繰り返し、生地を織り続けています。
この織機の名前は、ションヘル織機。
ションヘルとはドイツの織機メーカー名Schönherr GmbHです。

この尾州地域では、国産のシャトル織機を長年使用してきました。
そのシャトル織機は、ションヘル社型と類似しているので、
いつしかこう呼ぶようになったそうです。
ションヘル織機は、現在主流の最新織機と比較すると
1/5程度の非常に遅いスピードで生地を織り上げます。
尾州地域では、いまだにションヘル式自動織機を使用している機屋さんが存在しています。
このような織機は60年以上前に製造されたもので、
壊れたら直し、壊れたら直しを繰り返しながら稼働し続けている貴重な存在です。